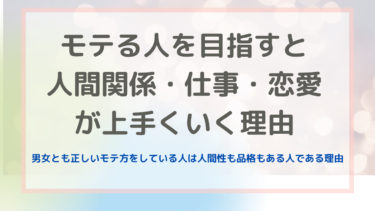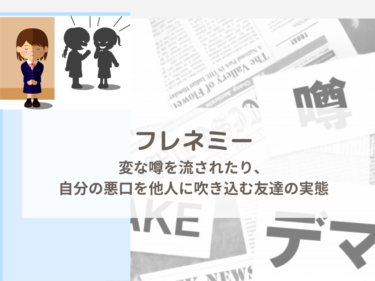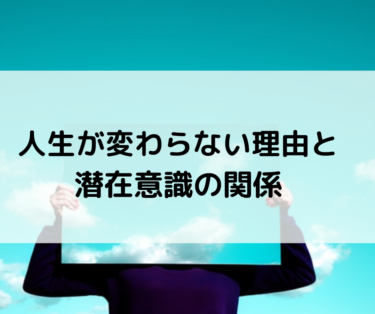自己肯定感が低いと生きづらさを抱えたり、他人に依存しやすくなったり、チャレンジも何もできないといった状況に陥ってしまいます。なので、できるだけ自己肯定感は高く保つことを意識したいですよね。
自己肯定感を上げる努力をしても下がることを同時にしていれば、結局変わりません。今回は、自己肯定感を下がってしまう、してはいけない行動パターンについて紹介します。
1.自分のことを嫌いになるような行動はしない
自分のことを嫌いになりそうな行動や自己嫌悪に陥ってしまうようなことをしていくと、自己肯定感が下がっていきます。
以下は、自己肯定感が低い人にありがちな行動ですが、このようなことを繰り返してしまうことで自分のことを心から好きになれなくなってしまいます。
■自分が嫌いになる行動パターンの例
- 自分にはできない、無理と決めつけてしまい、愚痴ばかり言って努力しない
- 寂しさを埋めるためにすぐに体を許してしまうけれど、自己嫌悪に陥る
- 自分の考えが言えず、周りに流されやすい
- 他人の悪口を言ったり、見下したりすることでストレスを発散する
残念だけど、このような行動を繰り返してしまう自分に憧れも抱かないし、あまり好きになれないのではないでしょうか?
他人であっても同じで、あまり尊敬できるところがなく、可愛そうな人に思えてしまいます。
本人は気づいていないけれど、自分で自己否定・自己嫌悪を引き起こす行動をしてしまっているのです。
一見、謙虚に感じられますが、自己嫌悪に陥ってしまうことを繰り返したり、自分の能力を否定して愚痴ばかりいって努力しない姿は、自分自身も本当は好きになれないから自己肯定感も下がってしまいます。
本人も苦しんでいるかもしれませんが、事情はどうであれ、自他共にいい印象は抱けないし、そういうことをしている人を好きになれないのです。潜在意識もそういうことはよく分かっているので、自己肯定感も下がってしまいます。
なので、上記のような行動はしないほうがいいと思います。どうしても他人に依存したい、
自分のことが好きになったり、尊敬できるような行動をすると、自己肯定感も上がって自信もついてきます。
2.他人の行動を見て嫌だと思うことはしない
他人の行動を見て嫌な思いをしたことはございませんか?
マナーが悪い、ぶつかっても謝らない、マウント、人の悪口や愚痴ばかり言って何もしない、上から目線、やる気をそぐことを言う、不誠実な対応・・など、他人の行動や自分がされたことで嫌だと思うことって多少はありませんか?
そのような自分が嫌悪感を抱くような行動を、他人が取っていても真似しない方が賢明です。
やっぱり、嫌悪感を抱くような行動をとってしまうと、気持ちよく生きれないし、まともな人から見ると品格がない人とみなされてしまします。そんなことをしてしまう自分も嫌になっていくので自信を持つこともできなくなってしまいます。
自己肯定感を上げる方法だけを見て、いくら自分が一番だと思い込んでも、嫌悪感を抱くような行動をしてしまうと自己肯定感は下がってしまいます。
3.自分を大切にしない

自分の意見が言えない、周りに流される・・・などといった方も多いと思いますが、自分の意見を否定して周りに合わせているので、自分を大切にできていません。
寂しがり屋で自分に自信がなく、他人に嫌われるのを過剰に恐れているタイプに多く見られます。
周りに流されやすく自分の意見を言えない人は、フレネミーやモラハラ系の餌食になってしまったり、押しに弱いのでダメな方にばかり流されてしまう場合もあります。
フレネミーやモラハラ系は、自己肯定感が低い人が大好物です。友達のフリをしては、ダメ出ししたりマウントをとってくる友達や、自分を大切にしてくれない恋人が周りにいたら要注意です。
寂しいからといって、気分が悪くなったりするような人と付き合わなくてもいいのです。尊敬できない人や一緒にいて気分が悪くなるような人ばかりに囲まれているのであれば人間関係を見直すことをおすすめします。
人間関係の断捨離や法則についての記事もご覧ください。
「いつも合わせてばかりいて疲れる」 「私は本当に、この人達と遊んで楽しいのか?」 「地元を離れてから話が合わなくなってきた」 このように思っていませんか? 友達は多い方がいい、自分と仲良くしてくれるのだから付き合わないといけない[…]
2対6対2の法則はご存知でしょうか? 2対6対2の法則は、会社や組織などで「成果の高い人材2割:平均的な人材6割:成果の低い人材2割」に分類されるという理論になるのですが、人間関係にも当てはまると言われております。 人間関係にお[…]
自分を大切にできるようになると、ストレスも軽減され自暴自棄に陥ることも少なくなるし、自己肯定感が低い人を餌食にするような人達も自然と消えていきます。
モラハラ、フレネミー、押しが強い人も、あなたの前では本性を見せなくなります。
自分を大切にすることで、他人も大切にできるようになるので余計なトラブルに巻き込まれることも少なくなるし、同じ自己肯定感が高い人から好かれるようになったり、他人から頼られるようになります。
4.自己肯定感を下げてくる人との交流
フレネミーなどの自己肯定感を下げてくる人達や、傷のなめ合いに陥ってしまうような自己肯定感が低い人とズルズルと関係を続けてしまうと、なかなか自己肯定感が上がりません。
例えば、自己肯定感が低い人達と一緒にいると、自信を持つことや前向きに目標を達成することが悪いような気がしてしまうし、フレネミーみたいな人は、自信を失わせ、良くない方向に自分を導くことが多いからです。
自分が変わろうと意識したのであれば、今までの人間関係を大きく変えることも必要です。最初は寂しい思いをするかもしれませんが、自分が成長していくことで新たな素敵な人達に出会えるようになります。
さいごに
自己肯定感を上げて、自分が一番だと思い込むなどして頑張っている方もいますが、自己肯定感が下がるような行動をしていては
自分が一番だと思い込むなどして自己肯定感を上げることばかり頑張っていても、自分も人間関係も一向に改善しないのは、同時に自己肯定感を下げるような行動をしているのではないでしょうか!?
いくら自分が一番でできる人間だと思い込んでいても、周りが見えていなかったり、自己肯定感を下げることをしていてはただの痛い人になってしまいます。
誰でも失敗はあるし、上手くいかないことから多くを学んでいくので、自己肯定感を上げて人一倍努力をしていてもなんかおかしいなと思ったことがあったら自分を見つめなおしてみてくださいね。
だれでもトライアンドエラーを繰り返すことで成長していきます。
こちらもおすすめ
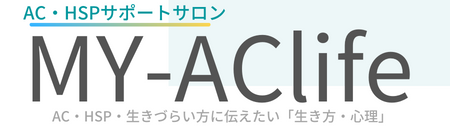

と言えない-他人に過剰に合わせてしまう理由-16-375x281.png)
と言えない-他人に過剰に合わせてしまう理由-14-e1658742816222-375x264.png)



と言えない-他人に過剰に合わせてしまう理由-17-150x113.png)